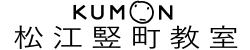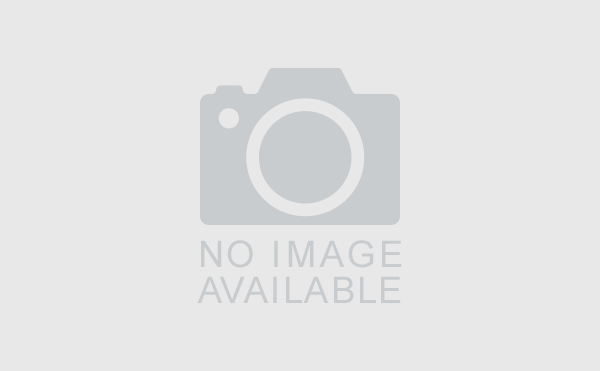教室だより(2019年3月)
羽撃け!! 竪町教室だより 2019年3月
2020年の教育改革は、すぐそこです。もうすでに「二極化」が進んでいます。
公文公の言葉より
「落ちこぼれというものをどう見るのか。落ちこぼれがけしからんということで、落ちこぼれなどをないようにするのが大切なのか。それならレベルを下げて、中学一年生になってから九九を教えるならば、落ちこぼれる子供は少なくて済みます。落ちこぼれがあるということは、それだけ教育に力をいれているからです。教育を盛んにしたら落ちこぼれがあって当たり前。そうだから教育することをやめたら、落ちこぼれなんか起こらないのです。ともあれ、ある一定の基準の設定せざる得ない、一斉授業の解決できない永遠の悩みではないでしょうか。(心に刻む200の言葉より)」
当時、落ちこぼれという教育問題が、社会問題として、クローズアップされ、まるでこのままの教育で子供たちはいいのかを問われていた時代で、「ゆとりの教育」にはいっていくときに、それに逆らうように公文公会長が言われたことを私は鮮明に覚えています。
今までは、黒板とチョークで一斉に教えてもらい、指示をきちんと受け止め、指示されたことを、指示通りにちゃんとやることが「賢い子」でした。「いっぱい覚える力」と「いっぱい覚えたことを思い出す力」が「学力」と言われてきました。だから、私たちには「指示を待ち」「教えてもらうことが勉強」という感覚が骨の髄まで染み込んでいます。
これから必要な力はズバリ「自分からやる力」です。
自分で進んで「学んで」自分で「試行錯誤」して失敗もしながら学んでいくやり方です。今までは、自主的:やるべきことが決まっていて、それを自分からやる。
主体的;何をやるかが決まっていない、自分で考えて判断して行動する。
人は困難があるから考えるようになる。考えると計画するようになる。考えると見えなかったものが見えてくる。考えることを放棄している人には何も見えない。チャレンジしている人には、どんどん見えてくる。
企業が求めている人NO.1はチャレンジ精神。NO。2は主体性。NO.3成長思考、NO.4考える力、コミュニュケーション能力だそうです
ところで、NO.1のチャレンジ精神とは、やったことのない問題、難しい問題、見たこともない問題に取り組むこと、とありました。竪町教室の子供たちは、80%以上が学年をこえて、2先以上へ、みたこともない、難しい問題に自分の力で毎教室日チャレンジし続けているのです。まさに、社会が求めているものです。
公文公は、「数学を教えるのではなく、数学で自学自習できる子を育てる(社会理科ではできないのです)のが公文式」だと言い続けられておられました。
■竪町教室からのお知らせ
◍3/27(水)はお休みです。
◍3/23(土)~4/6(土)は、春休みのため、水曜土曜ともに13時から21時で学習します。
◍4/20(土)は、新小2~中3生は、全員標準学力テストを行います。
◍水曜日のピーク時は、17時~19時、土曜日は14時~16時です。できれば避けて頂くか、ずらしてきて頂くと嬉しいです。
◍教室前の駐車場はアイドリングストップでお願いします。第2駐車場は(国道9号線入ったすぐ5台駐車スペースあります)アイドリングOKです。